毎月20日が過ぎると賃金台帳記入の仕事が出てきます。
事業所から給与明細を送ってもらったり、タイムカードを預かってこっちで給料明細を作ったりもしています。
この給与明細の後半の控除項目、つまり給料から引かれるモノ、社会保険料とか雇用保険料とか税金の計算方法などは、給与ソフトを使っていない少人数の会社で、よく間違いを見かけます。
じゃあこれ、どうやって計算するんだ?って問い合わせがあったので説明いたします。
比較的簡単な計算でいいのは雇用保険。給料の総額の1000/8です。建設業では1000/9となります。
健康保険と厚生年金には以前お話したように給料の平均を標準報酬と決め、それに1000/41などの率を掛けることになります。一度保険料が決まれば月々の変動はありません。少人数なら計算するよりそのまま保険料額を記載するほうが簡単です。
所得税はもっともややこしい計算方法になります。少人数ならば国税庁で配布している税額表をみて貰う方が簡単です。
エクセルなどを使って計算式を組み込むことも可能ですが、これにはプログラムの知識が必要になりますので、ここでは省略します。
住民税は昨年の収入に基づき、各市町村から納税額が通知されます。これを12で割った額を月々徴収しますが、端数は6月に足されるので、その後7月から翌年5月分までは通常同額です。
 難しいと思ったらどうぞお近くの社労士に依頼してみてください。たぶんほとんどの社労士は給料計算もやります。
難しいと思ったらどうぞお近くの社労士に依頼してみてください。たぶんほとんどの社労士は給料計算もやります。もちろん社労士でなくても給料計算はできますけど、労務の専門家だからこそ気配りできる部分が多くあるんです。









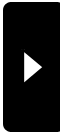
何でいまから来年度1年分を…と思われるかもしれませんが、実は来年度予算編成における人件費の重要な部分を占めているのです。給与担当は別にいますが、予算計上額の計算はいつも自分の役目。おかげでけっこう勉強になります。
僕も社労士試験受けてみようかな?
(その理由は4月30日の記事をご覧ください。)
今後社会保険庁が解体し、健康保険は県単位の運営になるとか、
厚生年金と共済年金を一元化するとか、様々な制度が変わってきます。
社労士も大変だよ~。